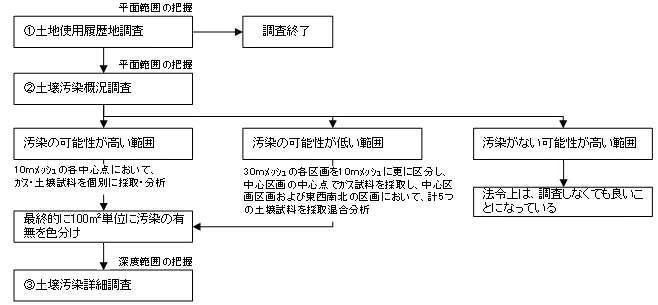土壌汚染対策法が施工され、土壌汚染問題が各方面にてクローズアップされ始めました。
対策法は住民の健康被害を防止するという観点で制定されましたが、現実には不動産価値を大
幅に減じるといった経済的側面でのデメリットのほうが注目されつつあります。
汚染した土地を放置することはなんら得策ではありません。むしろ早期発見、早期対策が企業リ
スクの回避に効果的です。
| ◆ | 土壌・地下水汚染調査対象物質 |
| ○第1種特定有害物質(揮発性有機化合物) | |
| 四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.3-ジクロロプロペン、 | |
| ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.3-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン | |
| 特徴: | 水に僅かに溶ける。一般的に水より比重が重いため深部まで浸透しやすい。 |
| 地下水面まで到達すると水平方向へ広がる。 | |
| ○第2種特定有害物質(重金属類) | |
| カドミウム、鉛、砒素、水銀、シアン、六価クロム、セレン、ほう素、フッ素 | |
| 特徴: | 表層部に溜まりやすい。客土による汚染が出やすい。 |
| ○第3種特定有害物質(農薬類およびPCB) | |
| PCB、有機リン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ | |
| 特徴: | 表層部に溜まりやすい。汚染事例としては極めて少ない |
| ◆ | 調査契機 |
売買形態例 調査の主旨 工場→住宅 住宅購入者への説明に必要 工場→工場 特に所有者が変更になる場合において、汚染の原因がどの段階で生じたのかを確認する。 住宅→住宅 一般には調査されない。 資材置場→住宅 製造施設がないが、資材の整備等に薬品等を使用している可能性がある為、実施することがほとんど。
(例)錆止め、塗装、研磨、潤滑油の使用等空地→住宅・工場等 過去に工場がなかったことを確認した上で判断。
| ◆ | 調査契機 |